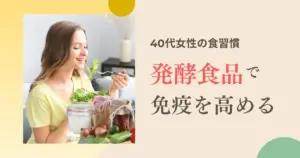お風呂に入るだけでもリラックス効果がありますが、そこにアロマを加えると「香り × 温浴」の相乗効果で、心も体も驚くほど軽くなります。
古代エジプトのクレオパトラはローズを浮かべたバスを愛し、ヨーロッパでもラベンダーやローズマリーを使った温浴は「自然療法」の一つとして親しまれてきました。
ただし精油をそのまま湯船に入れるのはNG。正しい方法を知らないと「香りが強すぎる」「肌にピリピリ感が出た」などトラブルにもなりかねません。
この記事では、初心者でも失敗しないアロマバスのルール・悩み別レシピ・安全に楽しむコツをまとめています。
- お風呂に精油を入れるときの正しい滴数と注意点
- 「直入れNG」の理由と乳化に使えるアイテム(塩・オイル・乳化剤)
- 快眠・冷え性・肩こり・むくみ・美肌ケアなど悩み別レシピ
- 入浴温度・時間・頻度のベストな目安
- 妊娠中や子ども、ペットと同居のときの注意点
- アロマバスをもっと楽しむセルフケアTips

アロマバスの基本ルール
精油は直接入れない
精油は水に溶けず表面に浮き、原液が皮膚に触れて赤みや刺激の原因になります。必ず乳化させましょう。
滴数の目安
- 全身浴:3〜5滴(湯量150〜200ℓ)
- 半身浴:2〜3滴(湯量100ℓ)
- 足浴:1〜2滴(洗面器1杯)
初心者は「少なめ」から試すと安心。慣れると好みの滴数を見つけられます。
入浴温度と時間
- リラックス目的 → 38〜40℃のお湯で10〜15分
- 疲労回復や冷え性 → 40〜41℃で15〜20分
- 快眠 → 就寝30分前、ぬるめのお湯で副交感神経を高める

乳化の方法(具体レシピ付き)
精油を溶かすためのおすすめ方法を紹介します。
- バスソルト:天然塩大さじ2に精油3〜5滴を混ぜ、お風呂に投入
- 植物油:スイートアーモンド油やホホバ油大さじ1に精油を加える
- 乳化剤:無水エタノール小さじ1に精油を混ぜてから湯船に
👉 手作りする場合は「保存せずその日のうちに使う」のが鉄則です。
▶︎ 初めて精油を買うときに「どれを選べばいい?」と迷ったらこちら。失敗しない選び方とおすすめ精油をまとめています👇


悩み別アロマバスレシピ
快眠バス
- ラベンダー:2滴
- オレンジスイート:2滴
- ゼラニウム:1滴
→ 心身をゆるめて眠りやすく。寝る前の習慣におすすめ。
▶︎ 快眠バスに欠かせないラベンダーの魅力を深掘り。リラックス効果やおすすめのブレンド方法はこちらで詳しく紹介しています👇

冷え性ケア
- ジュニパー:2滴
- ジンジャー:1滴
- サイプレス:1滴
→ 体を芯から温め、血流を促進。冷えが強い冬に◎。
肩こりリリース
- ローズマリー:2滴
- マジョラム:2滴
- ラベンダー:1滴
→ 血流を促進して筋肉の緊張をやわらげる。入浴後のストレッチとセットで効果UP。

むくみ改善
- グレープフルーツ:2滴
- ジュニパー:2滴
- レモングラス:1滴
→ 利尿・デトックス作用で脚のむくみをスッキリ。
美肌ケア
- フランキンセンス:2滴
- ゼラニウム:2滴
- サンダルウッド:1滴
→ 乾燥肌・年齢肌のケアに。お風呂後の保湿ケアと合わせると◎。

おすすめ精油と避けたい精油
アロマバスに向いている精油
- リラックス:ラベンダー、オレンジスイート、ゼラニウム
- 温め:ジュニパー、ジンジャー、ローズマリー
- 美容:フランキンセンス、ローズ、サンダルウッド
注意・避けたい精油
- 刺激が強い:シナモン、クローブ、オレガノ
- 光毒性あり:レモン、ベルガモット(入浴直後の日光NG)
- 妊娠中は避けたい:クラリセージ、ジャスミン

FAQ:よくある質問
Q. 妊娠中でも使える?
A. ラベンダーやオレンジスイートなど穏やかな精油は少量なら可。ただし必ず医師に相談を。
Q. 子どもと一緒でも大丈夫?
A. 3歳未満には精油の使用は控えましょう。6歳以上は大人の半量を目安に。
Q. 湯船に入れた際、あまり香りがしないのですが大丈夫?
A. お風呂場は蒸気や温度で香りがやさしく広がるため、鼻で強く感じにくいことがあります。
ですが、香りを強く感じなくても、呼吸や皮膚から精油成分はきちんと取り込まれています。むしろ「ちょっと物足りないかな?」くらいの香りの強さが、リラックスには最適です。
※精油を後から何滴も追加すると、肌への刺激や体調不良のリスクがあるので避けましょう。安心して楽しむには、最初に入れた滴数(3〜5滴程度)を守ってください。
▶︎ お風呂以外でもアロマを楽しみたい方に。ディフューザーでの安全な使い方と精油の滴数目安をわかりやすく解説しています👇


アロマバス+セルフケアTips
- 入浴後は水分補給を忘れずに
- ボディクリームやオイルで保湿ケアをすると美容効果アップ
- 軽いストレッチやマッサージで血流をさらに促進
- お気に入りの音楽やキャンドルと組み合わせると「自分だけの癒し時間」に

まとめ
アロマバスは「何滴?」「乳化」「精油選び」を守れば初心者でも安心して楽しめます。
- 快眠ならラベンダー+柑橘系
- 冷え性にはジンジャーやジュニパー
- 肩こりにはローズマリーやマジョラム
- 美肌・むくみなどにも応用できる
お風呂は毎日の習慣。そこに少しの精油を加えるだけで、セルフケアが格段に心地よい時間へと変わります。

あわせて読みたい関連記事
📌どの精油を買えばいいのか迷ってしまう方へ。初心者でも安心して使える定番の精油3本と、使い方のヒントをまとめました👇
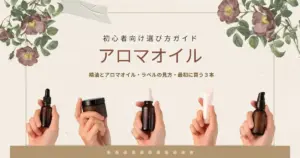
📌眠りの質に悩む方におすすめ。ラベンダーやオレンジスイートを使ったアロマケアで、更年期特有の不眠をやさしく整える方法を紹介しています👇
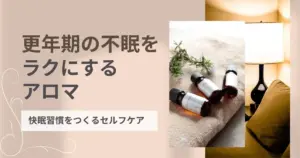
📌冷えや疲れが気になる方には、体の内側からのケアも大切。腸を整える発酵食品で、免疫力をサポートする食生活の工夫をお伝えしています👇